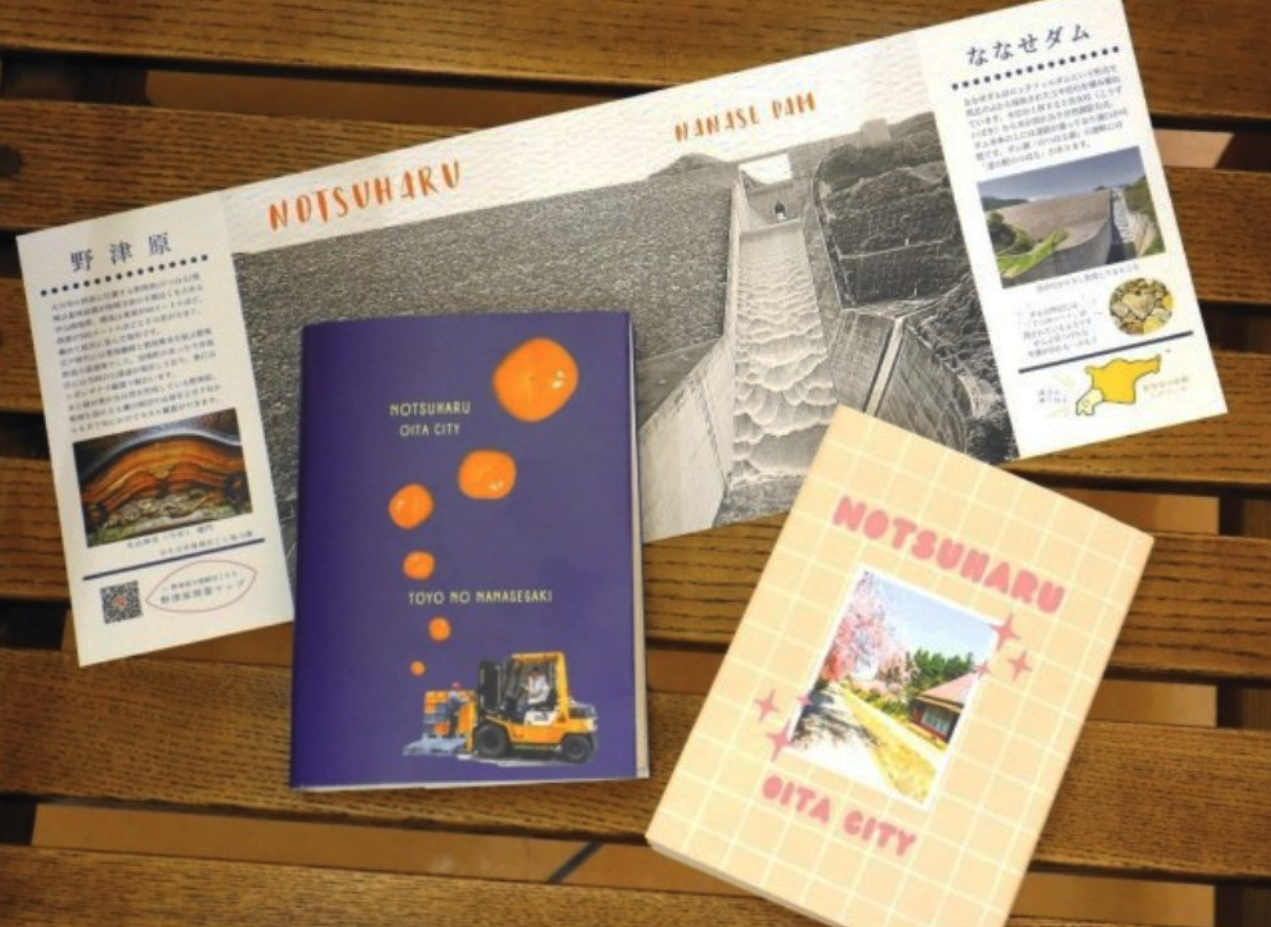- HOME
- make a buzz
- 戦後日本の安全保障

戦後日本の安全保障
日本国憲法が掲げる平和や人権といった(日本においては「戦後的」な)価値を重視する立場から、どちらかといえば(あるいははっきりと)リベラルだ、ハト派だ(あるいは護憲派だ)と自認している人たちは、ロシアのウクライナに対するあからさまな暴力と、それへの抵抗として続く戦争の間で、ウクライナの平和と人権をどうやって取り戻せばいいのか考えがまとまらず、頭を抱えているに違いない。
加えて、日本の安全保障に関する議論も、この世界史的な大事件に刺激されて一部ではやや過激化しているところもあり、ウクライナの情勢とどこまで直接に関係しているかは冷静に見なければならないが、少なくとも安全保障政策の再検討を促す勢いが強くなっていることには気づかずにいられない。日本の平和主義を肯定的に評価してきた人たちにとって、そのこともまた不安材料だろう。
さて、日本国憲法9条2項に「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」戦力不保持条項がありながら、自衛隊が存在していることをどう説明するか。自衛隊には何が認められ、何が認められないか。日本の安全保障政策は、この議論から逃れられない。それはもちろん、過去の「日本軍」を全否定することから戦後を始めた経緯によるものだ。
では、現在の、実際に存在している日本の安全保障体制は、その経緯との関係で、いかなる制約があり、どのような姿になっているのか。制度・政策・方針・運用は、どのようにデザインされていて、実際にどう機能しているのか。その全体像を俯瞰するのに最適な概説が本書の内容である。
- 日米安保条約
- 憲法9条
- 防衛大綱
- 日米ガイドライン
- NSC
この5つのトピックに分けて成り立ちから現在までの推移を振り返りながら、何が議論されてきたのか、その帰結として今どうなっているのか、そしていま何が問題なのかを解き明かす。安全保障政策に詳しくない読者にも、政治家や官僚、専門家たちの熱いドラマとして読める筆致で、入門に相応しい。
これを読んで痛感するのは、憲法9条2項、戦力不保持条項の威力だ。安全保障政策の隅々まで、法令の細部に至るまで、(当然だが)憲法に拘束されていて制約が多い。しかし、その拘束は、単に憲法に書かれていることにより自動的に保たれているのではなく、政治家や官僚が、そのように解釈と運用を積み上げてきた結果なのだ。この本には、拘束を解く解釈論上のテクニックがありながら、これまでそれが選択されなかった史実も書かれている。それはなぜか。最終的には、民意が政治に選ばせなかった、民主的統制が効いていたということになるだろう。
言い換えるなら、民意が変われば、政治が変わり、解釈が変わり、法令が変わり、運用が変わる可能性があるということ。今後の安全保障政策をどう考えるか、著者の示唆に同意するかどうかは別にして、この国の制度が、究極的には民意によって支えられていることを実感するにも、本書は有用だ。
戦後日本の安全保障
千々和泰明
中央公論新社
商品部
野上 由人